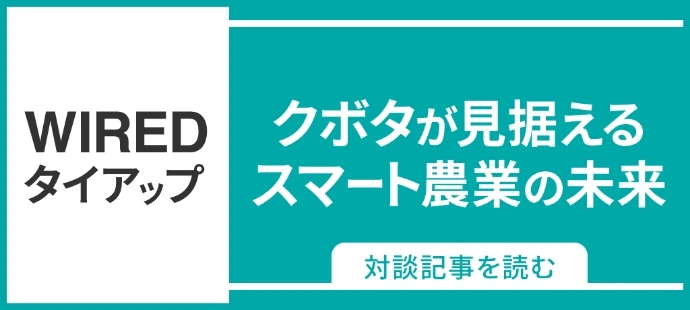いのちが輝き続ける
未来のために。
地球と人にやさしい、
プラネタリーコンシャスな農業を。
地球の未来が危うい
という事実。
プラネタリーバウンダリーという言葉をご存知でしょうか。
これからも地球で暮らし続けていく
ために、超えてはならない境界線。
CO2等の温室効果ガス濃度に
起因する「気候変動」や、
農地での肥料の過剰使用などによる
窒素・リンの「生物地球化学的循環」、
原生林の破壊などによって生物多様性や
生態系のバランスが失われる
「生物圏の一体性」など
9つの項目が設定されており、
最新の研究※では6つの項目で
限界を超えていると発表されました。
* “Earth beyond six of nine planetary boundaries,” SCIENCE ADVANCES (2023)
その原因は人間の歴史とともにありました。
18世紀後半の産業革命以降、
化石燃料をエネルギー源として産業が急速に発展し、
温室効果ガスであるCO2が大量に放出され続けてきたこと。
また人口増大に伴う宅地や農地の開拓によって森林面積が減少し、
CO2循環のバランスが大きく崩れたこと。
産業活動においてCO2以外の汚染物質も遠慮なく排出し続けていたこと。
それらが複合的に影響しあい土壌や生態系をも破壊していたこと。
人間だけの豊さを求め続けた社会に問題があったのかもしれません。
農業にできることは
ないだろうか。
地球環境の悪化は、農業分野において
生育不良や収穫量減少など、
影響をダイレクトに受けてしまいます。
一方で、農業が地球環境へ及ぼす影響も
無視することはできません。
現在の地球では人々が暮らせる土地の
約半分もの面積を農耕地が占めています。
その広大な農地で日々稼働する各種農業機械から排出される化石燃料由来の
温室効果ガスの影響は想像に難くありません。
さらに、土壌中からも大量の温室効果ガスが排出されているのです。
たとえば我が国の主食である米を栽培する水田からはメタンガスが、
過剰に撒かれた肥料を含む土壌からは一酸化二窒素が
それぞれ排出されています。
これらの事実は地球温暖化の原因であると同時に、
成層圏オゾンの破壊や海洋酸性化、土地利用変化や生物圏の一体性など
数多くのプラネタリーバウンダリーの項目と密接に関わり影響しあっているのです。
食べることは、生きること。
クボタは持続可能な地球環境と
豊かな食、豊かな社会をめざし、
今一度、農業を見つめ直しました。
地球と人にやさしい
農業のカタチ
- プラネタリーコンシャスな農業 -
地球と人にやさしい農業のカタチ
〜プラネタリーコンシャスな農業〜
プラネタリーコンシャス。
地球とすべてのいのちが、ずっと先まで
心地よく、幸せであり続ける状態。
そんな未来でありたいとクボタは思います。
農家に寄り添い続けてきたクボタらしい
カタチで
プラネタリーコンシャスな農業を
推進していくために何ができるのか。
その答えのひとつが
農業の無駄をなくし、
農家の負担を
軽減させることだと考えています。
そうすることで新しい価値が生まれ、
農業を魅力あふれる産業に変革していきたい。
ある未来予測では世界人口が21世紀末には
102億人になると予想されています。
その食料需要に応えるためにも、
既存農家の支援と新たな農家の確保は
世界的な課題です。
たとえば施肥や収穫などロボットに
任せられるような農作業は任せる。
生育状況の把握や作業計画は
AIやICTを活用しシステムで管理する。
地球環境へ負荷をかけない
効率の良い精密農業を、
誰もが手軽に実現できるサポートを。
未来の食と農業を守る、
プラネタリーコンシャスな農業に
クボタは取り組んでいきます。
農作業の完全無人化・グリーン化
いまだ多く残る手作業から
ロボット技術を応用した精密作業、
そして、農業だけでなく⼟⽊・建設作業までを
インプルメントやアタッチメントを付けかえ
完全無人で行うこと。
さらには、機械間のコミュニケーションにより、
協調しながらも自律作業を行う、複数機械の群制御(同時運転・共同作業など)。
加えて、新動力機構による
温室効果ガス排出削減への貢献。
これらの実現に向け、クボタは新たなコンセプト機として
汎用プラットフォームロボット
(Versatile platform robot)の研究開発を進めています。
ひとつは、様々なフィールドで
活躍できる高度な知能を有した
「Type: V」
もうひとつは、傾斜地や凹凸の
ある地形にも対応する
「Type: S」
Type: Vの特徴

01 完全自動運転
様々な情報やデータを分析し、必要な作業を検出、実行まで自動で行うことができます。
自らが取得したデータをもとに様々な提案や情報提供を行うなど、まるで相棒のように農作業をサポートすることも可能です。
02 車体の変形
車体の中央部を起点に、左右・上下・前後に伸縮が可能で、うね幅などのほ場の形状や作物の成長に合わせて機体の車幅・車高を変形できます。また左右や天井部、車体下にも多様なアタッチメント(インプルメント)を取り付けることで、これまで数種類の機械で行っていた様々な作業を1台で行うことが可能になります。
Type: Sの特徴

主に中山間地域の農家支援のために、
サードパーティ製モジュールとの連携も見越したオープンプラットフォーム仕様を
採用しているところにあります。
日本において中山間地域の農業は、耕地面積、総農家数、農業産出額が全国の約4割を占め、重要な役割を担っています。また里地里山と呼ばれ、雨水を一時的に貯留する機能(洪水防止機能)、土砂崩れを防ぐ機能(土砂崩壊防止機能)、生態系の保全といった多面的機能を有しており大切な財産でもあります。

中山間地域は傾斜地を多く含むことから機械化が思うように進んでいないため、いまだに農家の手による人力作業がほとんど。
まさに農業機械未開の地を切り拓く、画期的な一手として期待されています。
そして、傾斜地や凸凹のある路面でも器用に4本の脚を曲げ伸ばしすることで路面を捉え、高い駆動力を発揮し、デッキを水平に保ったまま走行することができます。
これにより安定した荷物の運搬やデータ収集や・防除・収穫などの高精度な管理作業が可能となり、今まで機械化・自動化が困難であった棚田や果樹園などの勾配のあるほ場でもより効率的な農業と省人化を実現します。
またオープンプラットフォームとして、ロボットアームやセンサーなどの様々なアタッチメントが搭載可能で、他社機器との連携も可能です。
農業関連の技術開発はクボタだけでなく、
国内外のスタートアップも
活発に行っています。
同じ志を持つ仲間たちとの共創によって、
プラネタリーコンシャスな農業を
よりスピーディーに、
より革新的に進めていきたい。
その技術と姿勢が評価され、
Type: S のベースとなるKATRは
「CES Innovation Awards® 2025」で
「Best of Innovation」を受賞しました。
この受賞を糧に、クボタはこれからも
地球といのちの未来に向けた取り組みを
加速させていきます。
データでつなぐ持続可能な食料システム

農業機械のグリーン化、無人化そして知能化。
クボタはそれらを統合し様々なデータから農業経営を見える化する精密農業システム(FMIS=Farm Management Information System)を開発。
この精密農業システムは、各種センサーや農業機械が取得した様々なデータだけでなく、気象予測や農学的知見などの情報も加味して、AIによる統合分析を行うことで病害の検出や生育状況の可視化を行います。
また作物の生育をシミュレーションすることで、収穫時期・収量・品質の予測や、それらを最適化しつつコストを最小化するためのピンポイント施肥や水管理の最適化などの高度な作業提案を行います。精密農業システムがこの作業提案をもとにType: V、Type: Sに作業指示を行い、熟練農家のような精密で無駄のない農作業を自動で行うことを実現します。
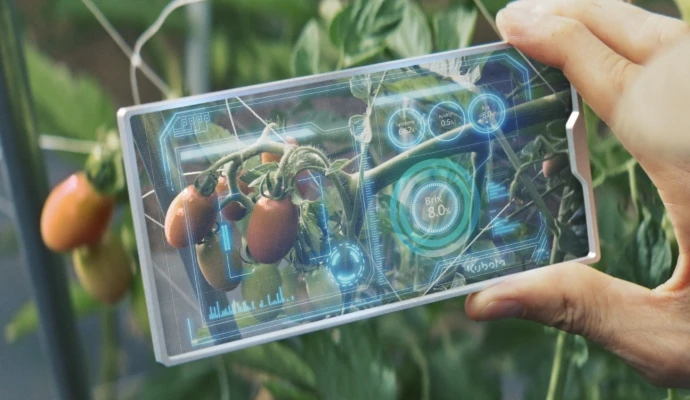
加えて、データを活用した農業をさらに進化させるために、必要な時に外部データと組み合わせて活用できるよう、精密農業システムでもオープンプラットフォーム化を推進しています。
こうした取り組みを通じて、複雑で様々な環境条件の影響を受ける農業において、データによるきめ細やかな管理を実施し、誰でも質の高い作物が生産できる農業を可能にしています。
また農家から消費者に届くまでの環境負荷のない最適な輸送方法の選定など、準備、生産、加工販売、消費という一連のフードバリューチェーンをデータで管理できるプラットフォームになることで、地球にも人にもやさしい持続可能な食料システムを確立していきます。
農業資源の有効活用
作物を育て収穫し、
消費者のもとへ届ける。
この一連のプロセスがいかに
地球と人にやさしいかを追求することは
とても大切です。
さらに農業というものをとらえ直してみると、
地球を良くするための資源が農業には
まだまだあると感じています。
たとえば収穫の際に発生する稲わらや
もみ殻などの副産物や、土壌が持つ力など、
農業そのものの資源を食料生産とは違う形で
有効活用することで、
地球環境へ
プラスの効果を発揮することができる。

たとえば、クボタのメタン発酵技術で稲わらから化学肥料の代替となる
液肥を抽出し土壌を汚染しないやさしい肥料として活用されている。
さらにメタン発酵によって発生したバイオガスをエネルギーに変換し、
その地域に還元することで温室効果ガス排出抑制にも一役買っている。
またCO2を排出しない太陽光発電の普及拡大のために
設置場所の確保が課題になっているが、
農地の上部空間を有効活用して発電する営農型太陽光発電もクボタは推進している。
土壌中の微生物の働きを活用した土壌発電も現在研究中だ。
農業をすること自体が地球にとって
良いことにつながるように。
農業の可能性をクボタは諦めず
追求していく。

農業は、みんなのものに。

農業の省力化とデータ化が進むことで、
これまでは農家が新しい試みをするにしても1つの作物に対して1年に1回程度、生涯をかけても数十回しかできなかったものが、デジタル上で何千何万それ以上のシミュレーションが可能になります。
農家がやりたいことを、すぐカタチできる。
だからこそ様々なことにチャレンジができる。
また新規就農者、農業未経験者にとっても「何を作りたいか」「どんなことがしたいのか」といった理想を“農の知”の力を借りて簡単に叶えられるようになります。
これからの農業は、もっとみんなのものになっていくでしょう。

一定の大きな量を安定した品質で生産供給する大規模農家や、規模は小さくても消費者が求める高栄養価、高付加価値の作物を生産供給する農家、農家という肩書きは持たず自ら食べる分は自分で育てたいと思う人、無農薬農法などこだわりを持って育てたい人、週末だけ農業に携わりたい人、都市に住みながら郊外の農地を遠隔で運営する人など。
一人ひとりの理想に応じた農業のあり方が、これからは選択できる。
農業を楽しむ人が増えると、心も豊かな人が増え、
社会全体の幸福度も上がるとクボタは信じています。