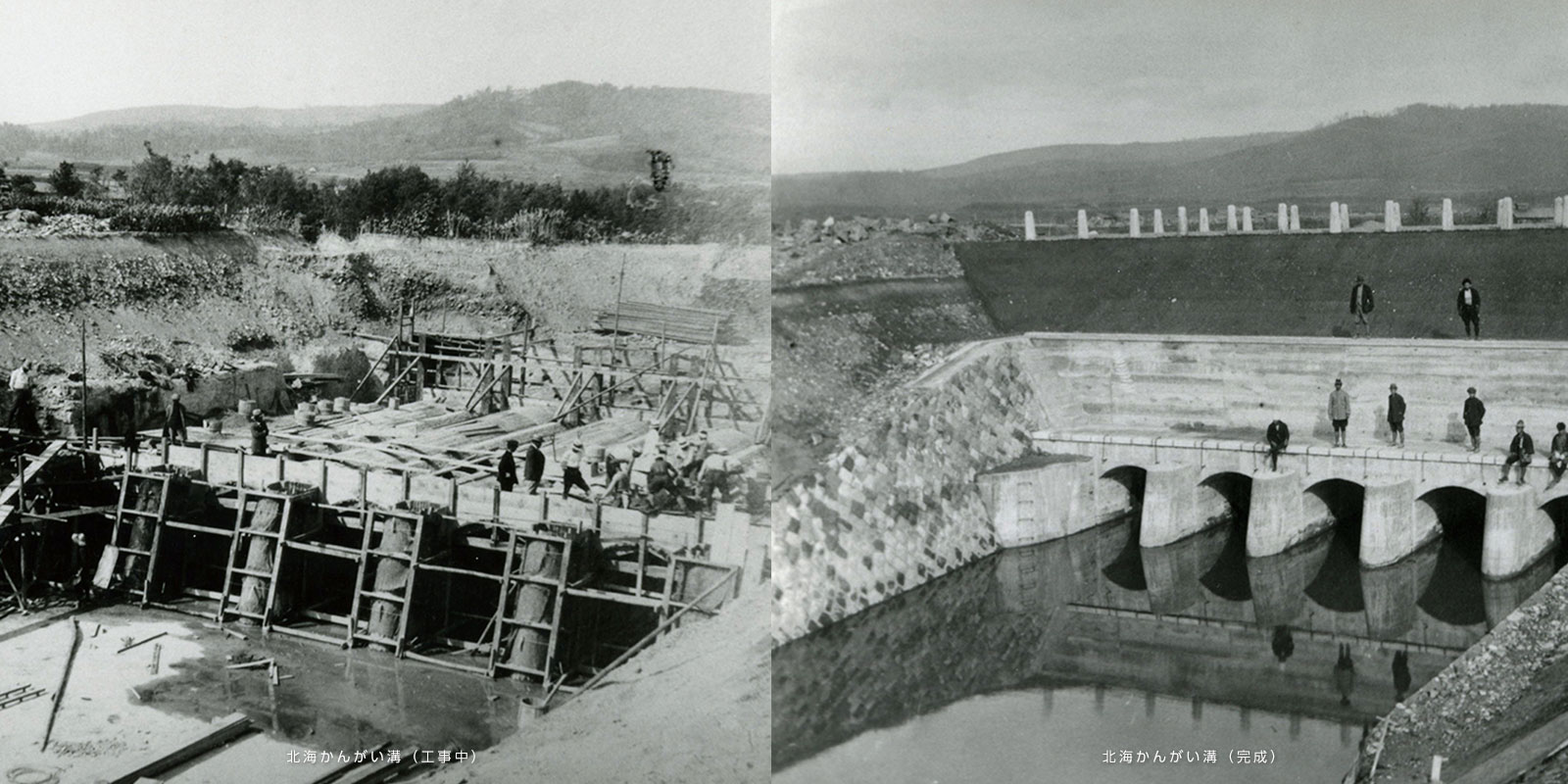北海道空知地域の米作りを支える「北海幹線用水路」がどのような役割を果たし、どのように管理されているのかを知るために各地を巡りました。
北海頭首工の管理


北海幹線用水路は、毎年5月1日から8月31日までの約120日間、水を流しています。 多いときで、空知川から毎秒約42.5トン取り入れています。1日にすると約367.2万トンになります。
北海頭首工(とうしゅこう)にある、北海幹線用水路のスタート地点です。 空知川から取り入れられた水は、田んぼを潤しながら、時速約4km(人が歩く早さくらい)でゴール地点の南幌まで約80kmの旅をします。


「監視カメラを使って、24時間体制で管理しています。 そのために、住まいもこの管理棟にあるんですよ」と話すのは、北海頭首工管理人の村田信次さん。
村田さんは、JR北海道に勤務された後、第二の人生としてこの地を選んだそうです。

村田信次さん


敷地内には北海水神宮があり、水利水運を司る守護神が祀(まつ)られています。 毎年、5月1日の通水式と、8月31日の断水式では、ここに関係者が集まって厳かに神事が行われます。


取水口には、ご覧のようにゴミも集まって来ます。これを定期的にクレーンで取り除き、きれいな水を守っているのも村田さんです。

北海幹線用水路の旅


赤平市にある北海頭首工から、さまざまなポイントを見ながら、南幌町の終点を目指しました。
北海頭首工を出発すると、北海幹線用水路は、しばらく道道227号赤平滝川線と併走します。 途中には、美しい散歩道も設けられています。


北海幹線用水路は幾つかの河川をまたぎます。こうした箇所では水路橋が設けられています。 水路橋は15カ所あります。
地域の暮らしを支える用水路の多面的機能


現在、北海幹線用水路は、米作りはもちろん、冷害から稲を守る深水灌漑(かんがい)用水、生活用水、防火用水、親水・景観保存機能、生態系保全機能、土砂崩壊防止・表土保全機能、洪水防止・水源涵養(かんよう)などの治水機能など、 水を活かした多面的機能で、地域の暮らしをさまざまな場面で支えています。
大きな水車が見えるのは、砂川市にある親水公園「流れのプラザ」です。 砂川市街地にある、用水路の上に整備された親水公園です。

北海幹線用水路が持つさまざまな役割について、水土里ネット推進室長・高柳さんにお話をうかがいました。

高柳広幹さん
(北海土地改良区 水土里ネット推進室長)
用水路の多面的機能をより活用するということで、 15年程前からいろいろなソフト面での活動をしています。 啓発活動、ウォーキング、ハーブの植栽などです。田んぼの学校の体験とか、 小中学校、高校・大学の見学会など、教育に活用したりもしています。 健全な水環境の形成や豊かな農村景観づくりに向けても、地域と一体となった活動を続けています」

美唄市にある光珠内調整池です。北海幹線用水路のほぼ中央に位置する調整池で、 貯水量約158万トン、札幌ドーム1個分の水を貯えることができます。
水が余ったときに貯めておき、不足すると補給します。 5月に田んぼに水を入れて土を平らに均す「代掻き(しろかき)」、 7月に田植え直後の稲を寒さから守るために水を深く入れる「深水灌漑」などに、 水がたくさん必要になり、補給します。
ここでは、平成18年より年に一度、7月末の日曜日に、北海土地改良区と地域が一体となって「ウォーキング大会」が実施されています。





夕張川揚水場です。この場所では夕張川から水を汲み揚げて、 その水をゴルフ場の上を通して、北海幹線用水路に注ぎ込みます。

ここが、南幌町にある北海幹線用水路の終点です。ここで、北海幹線用水路は地域の農業用水路に接続され、水の旅は終わります。
スタート地点の北海頭首工では、用水路の幅は14mありましたが、 約80kmに渡って田んぼを潤し、水量が減少しているため、 ここでは幅1.8mになっています。
豊富な水が可能にした直播栽培への挑戦

北海幹線用水路は、いまも改修工事をやっています。 将来に向けては、大型機械導入に伴う用水の確保や、 冷害対策として水を深くする深水用水の確保を目的とした改修も行っています。 これだけ広いので、必ず、どこかでやっています」
北海幹線用水路の豊富な水と、暗渠(あんきょ=地下に埋設された用水路)排水などの総合的な整備事業により、 直播(ちょくはん)栽培も始まっているそうです。