Our Challenges

地震大国で、街の「水インフラ」を守る
地震大国日本において
「水インフラ」を守れる街づくりに
多様なニーズで進化してきた耐震管※1
- 日本
- 2010年代
2010年、100年耐えうる耐震型ダクタイル鉄管※2GENEXを開発

1995年1月17日、日本の阪神地域および淡路島を中心にマグニチュード7.3という未曾有の直下型大地震が発生した。「阪神・淡路大震災」と呼ばれるこの地震は、交通網や港湾施設などのインフラ施設、水道やガス、電気、通信といったライフラインに甚大な被害をもたらした。被災地では約130万戸で断水が発生※3。特に老朽化した水道鉄管は破損が多く、公道下に敷設された配水管には3,600ヵ所余り、また各家庭に引き込まれている給水管にも20万件を超える破損事故が見られたという。この震災により、非常時でも安全な水を確保できる、地震に強い水インフラの整備が、日本全体の喫緊の課題として改めて浮き彫りとなった。そしてまた、クボタの「耐震菅」は耐震性の高さを示すこととなった。
いまや日本の水道の主要管材となっているのが、高い強度や耐久性・耐食性を誇るダクタイル鉄管だ。1957年からクボタが量産を始めたが、1964年にマグニチュード7.5を記録した新潟地震では、鉄管の継手の何ヵ所にも漏水が見られた。クボタは、その継手箇所からの漏水に着目。専門家へのヒヤリングと研究を重ね、ダクタイル鉄管の耐震性向上に尽力した。
そして1974年、地盤の動きに柔軟に追従することで継手の耐震性を向上させた耐震管としてS形を開発。そして1977年にはSⅡ形、さらに1993年には施工性を向上させたNS形へと進化させていった。1995年の阪神・淡路大震災でも、神戸市内に埋設されていた約270kmの耐震継手ダクタイル鉄管において、水漏れや破損の被害は皆無。その後の東日本大震災や熊本地震などを経て現在に至るまで、水道管路敷設距離3,650kmに被害ゼロという性能の高さを証明し続けている。

右:東日本大震災の津波にも耐えた耐震型ダクタイル鉄管(NS形)
そして、クボタの耐震型ダクタイル鉄管は2010年、耐震性の向上を追求するとともに、製品と管路敷設費の低減、省力と省人を視野に入れた施工性の大幅な向上、耐食性強化による長寿命化を実現した「GENEX」へと進化。その品質は日本と同じく地震多発地であるアメリカ西海岸でも水道管として採用されるなど、海外でも認められた。また、ダクタイル鉄管以外でも、日本国内で水道配水用としてすでに広く受け入れられているポリエチレンパイプも「水道事業ガイドライン」の「耐震管」認定を受けている。クボタは、多様なニーズに対応すべく、耐震性・耐食性だけでなく施工性や耐久性に進化してきた耐震管をもって、日本だけでなく世界の水インフラを地震から守っていく。

- ※1耐震管 継手が伸縮・屈曲し、かつ離脱防止機構によって抜けださない構造を有した管のこと
- ※2ダクタイル鉄管 管体がダクタイル鋳鉄という粘りがあり強靭な素材でできている水道管のこと
- ※3出典 総務省 消防庁「阪神・淡路大震災について(確定報)」より







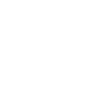 Our Challengesトップに戻る
Our Challengesトップに戻る