Our Challenges

60年に一度の大雨・大洪水の復旧
60年に一度の大雨がもたらした
タイの大洪水からの復旧を
力強く後押しした日本の排水ポンプ
- アジア
- 2010年代
2011年、移動式排水ポンプ車と発電機付浄水設備、タイで活躍
2010年代はじめ、多くの自然災害が世界中で起こった。日本で発生した東日本大震災やニューヨークを襲ったハリケーン・サンディ、フィリピンを中心にアジアで猛威をふるった台風など、自然災害の脅威はますます大きくなっている。こうした災害は人々の生命や財産、そして長年の開発によるさまざまな成果を一瞬で奪いかねず、中でもその被害者の9割は途上国の国民であるといわれている。グローバル化によりヒト、モノ、資本が国境を越えて大量に移動するようになった今、災害の影響は被災地のみならず、世界各国に即座に波及することになる。開発途上国では、自然災害が「貧困削減·持続可能な開発の大きな障害」となっているのである。※1※2


2011年にインドシナ半島を襲った大雨は、歴史的な大洪水をもたらし、工業国として姿を変えつつあったタイに大きな打撃を与えた。この大洪水による被害は、数ヵ月にわたり長期化した。要因のひとつとしては、急ピッチで進められた工業団地化や都市化により、これまで治水機能を果たしていた水田の面積が減少し、保水能力が低下していたことが挙げられる。そこに貯水可能な容量を超える大雨が降り、ダムの決壊を避けるために大量に放水。さらに、国土が平坦で河川の勾配も緩やかなため、水がたまりやすい地形でもあった。
大洪水からの復旧においてクボタが担った役割は、浸水した首都バンコク北部の7つの工業団地で、一刻も早く排水を行うためのポンプを開発することだった。タイに進出する日系企業の3分の1、約450社が大きな被害を受けていたことから、日本政府はJICA(国際協力機構)による国際緊急援助隊専門家チームの派遣を決定。クボタが開発したポンプはチームとともに派遣された。排水用のポンプには、強力であることはもちろん、車両に搭載でき、人力による設置・撤去を可能にするため徹底的に軽量であることが求められた。その結果、開発された重量約30kgのポンプは自家発電機と同一車両に搭載することで、世界にも類を見ない自立性・機動性に優れた機能を持つこととなった。

そして、ロジャナ工業団地内の排水活動にあたったクボタのポンプ車は、連日気温30℃を超える猛暑の中、7日間連続24時間体制で稼働。その後も現地で排水活動を続け、約1ヵ月間その実力を発揮した。また、クボタの支援はさらに続いた。工業団地内では浄水場が被災し、工業用水が供給されない状況に陥っていた。そこで、ユニット型の発電機付浄水設備をタイ政府に寄付。工場内の洗浄や機械設備の清掃・修理に必要となる工業用水を確保することで、工業団地内のスムーズな復旧活動を後押しした。

社会に役立つモノづくり、それがクボタの創業時からの精神。時にその思いは、国際協力という形で現在にも繋がっている。クボタはこれからも自然災害に備え、復興・復旧に貢献できる水環境製品の開発と提供を通じ、災害に強い国づくりをアジアから世界へと広げていく。
- ※1出典 外務省「2014年版 政府開発援助(ODA)白書 日本の国際協力」より
- ※2出典 経済産業省「通商白書 2012年版」より






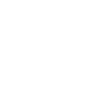 Our Challengesトップに戻る
Our Challengesトップに戻る