Our Challenges

地震多発地帯ロサンゼルスに選ばれた技術
アメリカの地震多発地域、
ロサンゼルス市が導入を決めたのは
大震災を耐え抜いた日本の耐震技術
- 北米
- 2010年代
2013年、ロサンゼルス市が耐震型ダクタイル鉄管「GENEX」を採用
日本に敷設されている水道管の約60%が「ダクタイル鉄管」※1であり、日本の水道の主要管材といえる※2。そもそも「ダクタイル鋳鉄」とは1948年にアメリカで発明されたもので、当時、材料分野における「今世紀最大の発明」として世界中から注目を集めていた。高強度で伸びがあり、鋳鉄本来の耐食性や鋼に近い強靭性を兼ね備えていたが、実製品に応用することはきわめて難しいとされていた。1954年、クボタはダクタイル鋳鉄を大口径ダクタイル鉄管として製品化することに成功。さらに1957年には量産化を実現させた。そして地震大国である日本において、クボタはダクタイル鉄管の高い耐震性や優れた耐食性といった特長を有効に生かし、さらに独自の耐震構造を持つ「耐震管※3」として高度化させてきた。


一方、アメリカにも日本同様の地震多発地帯があり、長年にわたり水道管路の耐震化を検討していた。地震多発地帯のひとつが西海岸のカリフォルニア州であり、過去何度も大地震を引き起こしてきたサンアンドレアス断層が走っている。厄介なことに、生活と経済を支える重要な水を供給する施設とパイプラインもまた、その危険な断層の上に設置されている。もし大震災が発生したら、水インフラが一気に壊滅してしまう恐れがあった。そのためLADWP(ロサンゼルス水道電力局)では、耐震性のあるパイプネットワークの構築が喫緊の課題となっていた。
そのような状況の中、日本で発生した阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大地震でも一切破損しなかったクボタの耐震型ダクタイル鉄管が、LADWPの目に留まった。現地との打ち合わせを重ねる中でクボタが訴求したのは、地震が起きてもパイプ間の接合部が伸び縮みして地盤の動きに追従し、管が外れることがないという構造だった。そのような機能性や大きな地震に耐えてきたという実績を高く評価したLADWPは、「100年の使用に耐えうる鉄管」をコンセプトにクボタが開発した最新の耐震型ダクタイル鉄管「GENEX」を、2013年にアメリカで初めて採用した。以後、クボタの耐震管は、カリフォルニア州からオレゴン州などへ試験導入が広がっている。

1904年、鉄管の量産体制を可能にする「立吹回転式鋳造装置」を開発し、日本初の水道管の量産に成功して以来、「鉄管のクボタ」として鉄管の耐震性・長寿命性などを進化させ続けてきた。これからもクボタの耐震管は、時代や国境を越え、地面の下から世界の水インフラを支え続ける。

大口径耐震型ダクタイル鉄管
- ※1ダクタイル鉄管 管体がダクタイル鋳鉄という粘りがあり強靭な素材でできている水道管のこと
- ※2出典 平成26年度 日本水道協会水道統計より
- ※3耐震管 継ぎ手が伸縮・屈曲し、かつ離脱防止機構によって抜けださない構造を有した水道管のこと






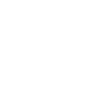 Our Challengesトップに戻る
Our Challengesトップに戻る