Our Challenges

下水処理から挑む、CO2大幅削減
暮らしを支える下水処理施設
CO2の大幅削減に挑み、
循環型社会への一歩につなぐ
- 日本
- 2000年代
2009年、灯油から天然ガスへの燃料転換で、さらなる大幅なCO2とコスト削減に成功

1997年に合意された「京都議定書」では、国家間での地球温暖化防止対策が議論され、各国で温室効果ガス削減に向けた活動が進められてきた。日本では2008年から2012年の間に、1990年度比で温室効果ガス6%の削減目標が定められた。そのような中、ECO先進都市である静岡県浜松市では、2003年に「地球温暖化防止実行計画」を策定し、市のさまざまな事業からのCO2排出量の低減に積極的に取り組んでいた。
浜松市が保有する施設の中で、最もエネルギーを使っていたのが下水処理施設だった。中でも最大規模である中部浄化センターでは当時、実に市の施設全体の9.2%ものCO2を排出していたため、至急対策をとる必要があった。そこで2005年、浜松市はクボタの循環流動焼却炉を導入した。この循環流動焼却炉は、3つの優れた環境特性を持っていた。1つ目は、焼却の際にダイオキシン類※1が発生しにくいこと。2つ目は、省エネ・高効率であるため全体としてCO2削減につながること。そして3つ目は、CO2の約300倍もの温室効果を持つN2O(一酸化二窒素)の排出が大幅に削減できること。さらに、これらの環境特性に加えコンパクトで、しかも低燃費。また、発生した焼却灰をセメントの原料としてリサイクルすることも可能であった。そのためN2Oの大幅削減だけでなく、2008年には、CO2も2005年度比で9.19%の削減を達成した。

しかしその後、さらなるCO2削減をめざす中、2008年に原油価格が1バレル140ドルに。焼却炉で使っていた灯油価格も高騰した。クボタは、コスト削減の必要性に迫られた浜松市から、循環流動焼却炉の天然ガスへの燃料転換要請を受け、直ちに技術、コスト、工期などの試算に取りかかった。運転中の焼却炉の燃料を転換する工事は前例がなかったこともあり、特に関係者が恐れていたのは、炉の運転が停止することだった。そこで浜松市とクボタ双方の技術者が検証を重ね、灯油バーナーを残したままガスバーナーを増設。それにより運転を続けながらも、限られた期間内での燃料転換が可能となったと同時に、CO2とランニングコストの大幅な削減をも実現した。2000年代、環境問題に取り組んでいたクボタにとって、このチャレンジは循環型社会の構築へ向けての大きな一歩となった。

右上:ガンバーナーに供給される天然ガスのガス圧力計
右下:焼却炉に設置されたガンバーナーユニット
- ※1ダイオキシン類 大変毒性が高く、一般環境中では分解されにくい物質のこと





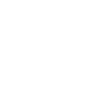 Our Challengesトップに戻る
Our Challengesトップに戻る